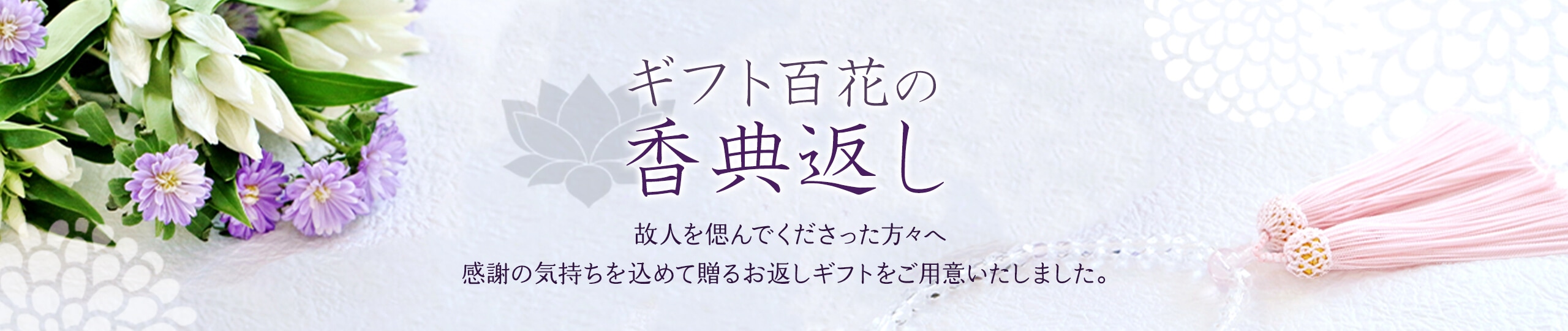

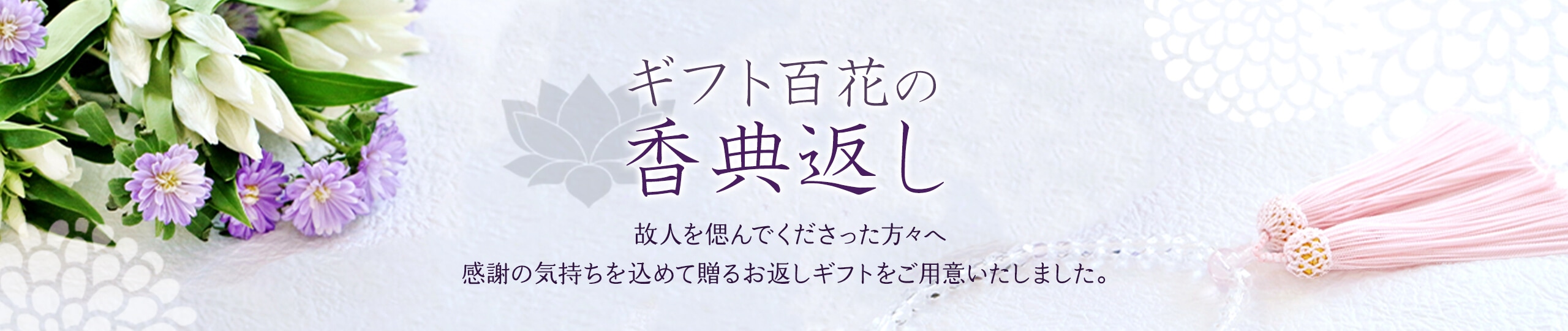


香典返しとは
お通夜や葬儀で故人にお供えいただいた香典への
お返しが香典返し(満中陰志)です。
香典返しには、不幸な出来事をあとに残さないという考えから
お茶菓子などの消えものが好まれ、
そのほかでは実用的なタオルやカタログギフトも定番です。
香典返しに人気のギフトをランキング形式でご紹介。香典返しのギフトに迷われたときの参考にしてみてください。
No.1

今治謹製
極上タオル バスタオル(木箱入)パープル
極上タオルを高級感あふれる木箱へお入れしました。
送料無料5,900円(税込)
ご購入はこちら
No.1

銀座千疋屋
銀座フルーツフィナンシェ 4種類 計12個
フルーツ果汁を生地に混ぜ込み、果肉をトッピングした、香り高いフィナンシェです。
送料無料3,564円(税込)
ご購入はこちら
No.1

東京・新宿 花園万頭
花園 銘菓詰合せ
代表銘菓「ぬれ甘なつと」をはじめとした、人気和菓子の詰合せです
送料無料5,400円(税込)
ご購入はこちら
No.1

〜2024/2/1お届け 袋布向春園本店 日本銘茶巡り
日本銘茶三都巡り「 麗 」-Uraraka-
上質な茶葉を厳選した詰め合わせです。「一杯の幸せ」をご堪能くださいませ。
送料無料4,860円(税込)
ご購入はこちら
No.1

〜2025/1/31 お届け
有明海産味&しじみ醤油味付のり G
風味豊かな味付海苔と、宍道湖産大和しじみ使用の醤油を使った味付海苔を是非ご賞味ください。
送料無料 5,400円(税込)
ご購入はこちら
No.1

エラボッカ
アメジスト5,280円(税込)コース
グルメやブランドはもちろん、体験型ギフトもご用意した1冊です。
送料無料5,720円(税込)
ご購入はこちら
有名メーカーのタオルや選べるカタログギフトなど、
センスのいい香典返しのギフトをカテゴリー別にご用意しました。
香典返しは、いただいた香典の額の半分が相場といわれています。
こちらでは予算別にご用意しました。
お悔みいただいた方へ感謝の気持ちを込めて
お返しを選びましょう。
香典返し用に仏事用の掛け紙(のし紙)や
包装紙のサービスを無料で行っております。
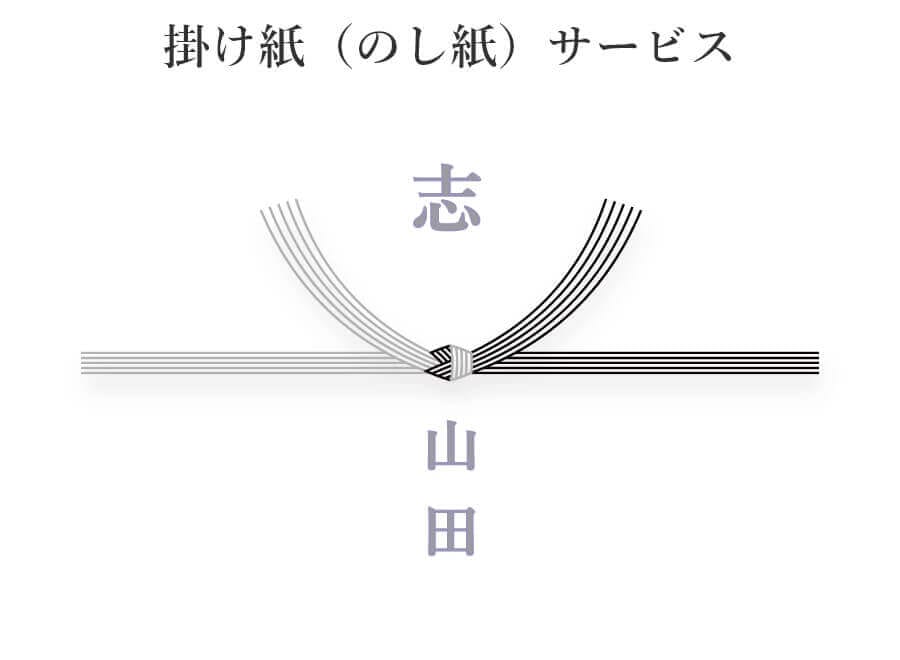

お届け先が多いお客様におすすめの
便利なサービスもございます
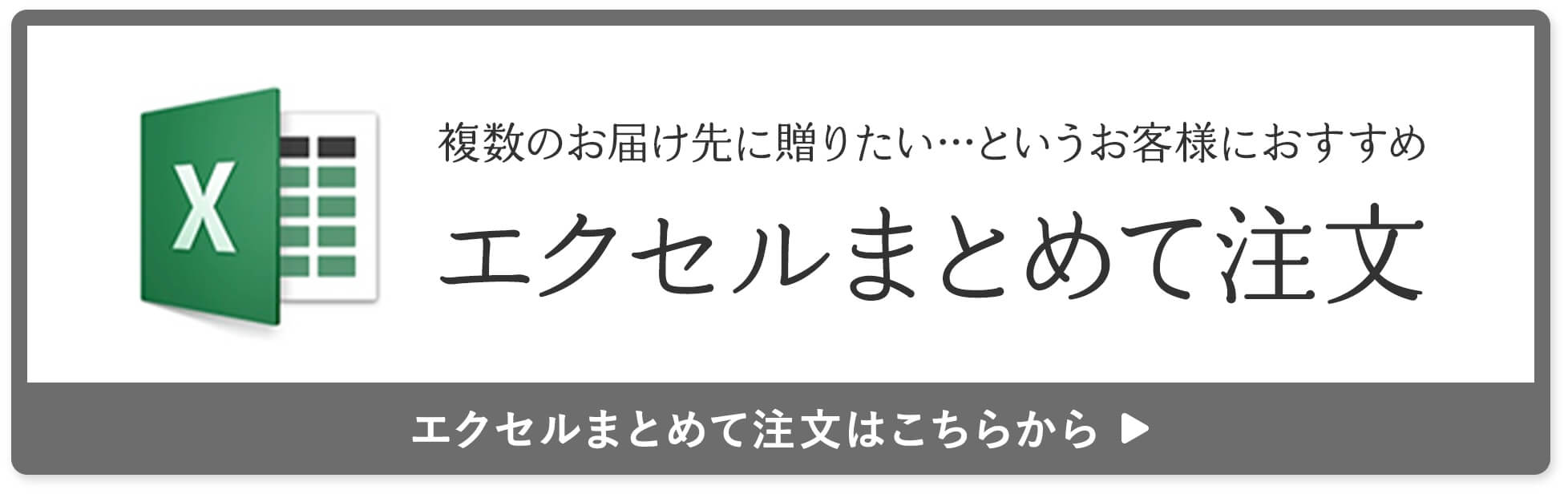
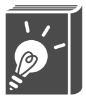
香典返しとは一般的にお通夜や葬儀で故人にお供えいただいた香典へのお返しの品物が香典返し(満中陰志)です。香典返しには地域の慣習や宗教による違い、人気の品物などさまざまなマナーが存在します。
宗教や地域によって異なりますが、四十九日の後が一般的と言われています。
香典返しは「半返し」、いわゆる「半分くらいの金額のものを返す」が一般的です。香典の相場が5000円〜10000円くらいと言われていますから、その半分くらいの金額が目安とされています。
送るタイミングについても宗教的なもので変わってきます。一般的な仏式では「四十九日」の法要が行われた後にお礼状を送ることが多いです。
宗教や地域によって異なりますが、表書きは「志」が一般的です。水引の色も黒白が一般的ですが、関西地方では黄白のものが使用されることが多いです。
香典返しで一般的なのが「消えもの」である「お茶やお菓子」日常的に消耗する「タオル」といわれています。金額のわかる商品券や、高額すぎる品物は避けた方が良いでしょう。
香典返しは四十九日後にお渡しするのが一般的なのに対し、「即日返し(当日返し)」と言って、忌明けを待たずに通夜や葬儀の当日に一律の金額で香典返しの品物をお渡しをすることもあります。
慶弔見舞金から香典が出た場合には、基本的にはお返しをする必要はありません。社員一同という形でいただいた場合には、皆で分けられるようなお菓子などがおすすめです。
香典返しはあくまでも香典に対するお礼なので、兄弟や子供などの親しい間柄であっても、お礼の気持ちを伝えるためにお返しするのがよいと考えられています。
香典返しをしないのは必ずしも非常識であるとは言えません。一家の働き手を亡くし、その子どもが小さい場合などは経済的な問題もありますからお返しを省略しても良いとされています。また、地域によっても風習が異なります。
香典は、日本の文化の中で様々な場面で贈られるお金です。特に葬儀や法要の際には、喪家に贈る香典が一般的です。企業で働いている方々は、時には会社関係者、たとえば上司や同僚、またはその家族の方々の葬儀に参列し、香典を贈ることがあります。
香典を贈る際には、その書き方に一定の決まりがあります。一般的に香典袋は、通常、水引のついている「外袋(外包み)」とお札を入れるための「中袋(中包み)」の2つの部分から構成されています。中袋にはお金を入れ、それを外袋で包む形となります。
香典袋は、外袋と中袋の2つの部分から構成されています。外袋には表書きと名前、中袋には金額と住所が書かれます。ただし、書き方には香典ならではのルールがありますので、注意が必要です。特に葬儀での香典袋は、薄墨の筆ペンを使用するのがマナーです。
香典袋の書き方には、いくつかの注意点があります。まず、香典の外袋と中袋にそれぞれ記入する項目が異なるため、適切な箇所に適切な情報を記入することが重要です。香典の外袋には贈り主の名前や表書きを、香典の中袋には金額や住所を記入します。
香典とは、通夜や葬儀でかかる突然の出費を助け合う意味があります。供花や線香などの代わりに供えるお金であり、故人との関係や葬儀の種類、法要などによって金額が変わります。一定の相場やマナーが存在するため、厳粛な葬儀の場での粗相や礼儀知らずにならないように、事前に確認しておくことが大切です。
会社で香典袋を書く際にも、書き方や包み方、渡し方など香典にはマナーがあります。それを知らずに自己流で香典を贈ると、ご遺族への配慮が足りず、恥をかく可能性もあります。葬儀に参列する際は、香典渡す際の基本的なマナーを心に留めておきましょう。
キリスト教か神道かを葬儀の案内の文章で確認できる場合もありますが、会社での関係性において事前に仏教の宗派まで把握できるケースはほとんどありません。必ずしも宗派に合わせた香典袋の表書きを用意する必要はありませんが、各宗教や宗派における香典袋の書き方のポイントを押さえて香典を渡すことが重要です。
葬儀や告別式に用いられる香典袋には、「御香料」「御香典」「御霊前」などの表書きが一般的に使われます。また、仏教の中で(浄土真宗を除く)は、人が亡くなってから四十九日後に成仏するという考え方があります。そのため、四十九日以降の法要に持ち寄る香典袋には「御仏前」の表書きの香典袋が適切です。
葬儀の際に持ち寄る香典には「御霊前」「御榊料」「御玉串料」の表書きの香典袋が用いられます。故人が神になるとされる五十日祭以降の式年祭では「御神前」の表書きの香典袋を使用しましょう。
キリスト教式の表書きは、一般的にはカトリックとプロテスタントの2つのタイプに分かれます。カトリックの場合は、「御花料」「献花料」のほか、カトリック独特の「御ミサ料」の表書きの香典袋が使われます。プロテスタントでは、「御花料」「献花料」の他に、プロテスタント独自の「忌慰料(きいりょう)」と呼ばれる表書きの香典袋が用いられます。
一般的には、「御霊前」は宗教や宗派を問わず使用できる表書きとされていますが、もし葬家が浄土真宗やプロテスタントであった場合、この香典袋の表書きは適切ではありません。そのため、宗教や宗派が分からない場合は、お香を供えるという意味を持つ「御香料」「御香資」「御香奠」の表書きの香典袋を用いるのが最も確実な方法です。
個人で香典を渡す場合、香典袋の外袋の中央、水引の真下に自分のフルネームを書きます。この際、香典を出した人が明確に分かるように、香典袋にフルネームで書くことが重要です。
会社全体から香典を贈る場合、一般的には会社の社長の名前で香典を用意することが一般的です。社長の名前が中央に配置されるように注意して「代表取締役〇〇〇」と香典袋に書きましょう。
会社の上司の代理として葬儀に参列する場合、香典袋の表書きは下半分の右側に「会社名」、「部署・役職名」を記入し、その下に会社の上司の名前を書きます。名前の下には、「代」と書き添えてください。
基本的に香典の中袋には氏名や住所、包まれた金額を書きますが、一般的な書類と違い香典の中袋には決まった書き方があります。
香典袋の中袋とは、通常2枚重ねになっている香典袋の内側の袋のことを指します。形状は一般的な封筒の形をしており、遺族に香典として渡す現金を中袋に入れます。
香典袋の中袋に名前を記入する際は、封筒の裏面の左下にフルネームを記入します。複数人で香典を持参する場合は、その人数分の名前や団体名を香典袋にしっかりと記入しましょう。住所の記載については、必要性を疑問視される方もいるかもしれませんが、例えばお葬式後に家族から別途返礼品が送られる場合などに香典返しを送る際に利用されることがありますので、できるだけ香典袋には住所を記載するようにしましょう。
葬儀や葬式について調べている中で、香典の相場や適切な用意方法に戸惑っている方もいるのではないかと思います。特に、故人が法人、会社関係の方である場合は、正しい判断をするためにポイントを押さえることが重要です。
会社関係の方への香典の相場は、その人の役職によって異なることを覚えておく必要があります。
上司の場合、故人が自分の上司であった場合、香典の相場は5,000円から1万円程度ですが、これは出す人の年齢によって変動します。直属の上司であるか、あるいはどれだけお世話になったかという観点でも金額は異なります。
もし故人が自分の部下であった場合、香典の相場は3,000円から1万円程度ですが、これは出す人の年齢によって異なります。このようなケースでは、同僚の場合とは異なり、香典を出す立場が変わります。
元社長や本会長などの会社OB であった場合、香典の相場は5,000円から1万円程度ですが、これは故人との関係性によって変動します。
一定の規模の会社では、通常は役員などがまとめて香典を出すことが一般的です。役員など代表者が連名で香典を出す場合には、個人で香典を出さないように注意が必要です。これは社内トラブルの原因となり、また香典を2度渡すことはマナー違反とされます。
「社葬」とは、企業が主体となって行う葬儀を指します。会社の創業者や社長、会長など、企業の設立や発展に大きく貢献した故人を偲び、その功績を讃え、感謝とともに弔意を表す場として行われます。
社葬や合同葬は、通常業務時間内に行われるため、一般的には企業役員や葬儀の進行を補助する係員のみが参加します。したがって、一般社員としては特に何もする必要はありません。
会社役員や代表者、社⾧の場合は、社葬が行われることがありますが、一般の社員でも業務中に事故や病気などで亡くなった場合には社葬が行われることがあります。社葬が行われる場合、通常は4〜5人程度の社員が手伝いに参加することが一般的です。
取引先やビジネスパートナーの葬儀や慶弔事に参列する際に、香典を送ることや、社会人になると、突然の訃報を取引先から受けることがあります。その際には、故人との別れを惜しむ一方で、思わぬ間違った対応をしてしまうと、ご遺族や取引先からの信頼を失う可能性もあります。
訃報を受けた場合、まずは上司に相談してください。仕事上の関係で受け取った訃報には、会社としての適切な対応が求められます。親しい関係であっても、個人の裁量で対応を決めず、まずは上司や担当者に訃報を伝えましょう。
通夜や葬儀に参列できない場合、お悔やみの気持ちを伝えるために弔電を送ります。葬儀の日程が確定したら、すぐに手配をします。弔電はNTT、郵便局、インターネットを通じて申し込むことができます。通夜や告別式の前日までに弔電が届くよう手配するのが一般的ですが、間に合わない場合は、弔電ではなくお悔やみ状を送ることが望ましいとされています。
取引先関係者の弔事で香典を包む際は、金額だけでなく相手の状況も考慮し、適切なタイミングを見極めることが重要です。
取引先の方が亡くなった場合、社葬の手伝いに行くことがあります。
もしも手伝いに行くことになった場合、取引先の葬儀で手助けすることは緊張しますが、役割を果たすことで関係が改善され、自社にとって好ましい結果につながります。
職場の同僚や上司、部下の親が亡くなった際には、業務の引き継ぎだけでなく、通夜や葬儀への参列や香典の包み方なども検討する必要があります。
社会人になると、職場で働く中で同僚が亡くなることもあります。このような場合、通常は会社の規則に従って葬儀や告別式への参列の可否や香典の金額について決めます。同僚と親しい関係であれば参列することもありますが、それ以外の場合は通常は指示がない限り参列しません。同僚の訃報を受けたら、上司に報告し、適切な対応を確認しましょう。
同僚が亡くなった場合、告別式への参列や手伝いを依頼されることもあります。会社から通夜や告別式の手伝いの申し出がある場合は、人事部や上司を通じて各部署から協力を求められることがあります。依頼があれば、その名誉ある任務を喜んで引き受けることが一般的です。
職場の同僚の告別式に参列する際には、特に礼儀作法に気を配る必要があります。告別式は火葬場のスケジュールに合わせて行われるため、決まった時刻に厳密に始まります。地域によっては前火葬を行う場合もありますが、どちらの場合でも遅刻しないように時間に余裕を持って会場に到着しましょう。
故人が職場の同僚であった場合、香典の相場は3,000円から1万円程度です。ただし、この金額は出す人の年齢や立場によって異なります。親しい関係であれば、多めに包むこともありますが、同僚全体の足並みを揃えることが大切です。
香典を包む際に知っておきたい注意事項はたくさんあります。冠婚葬祭では作法や縁起担ぎが重要視されるため、失礼のないように事前にマナーを把握しておくことが大切です。
香典の相場はありますが、最終的に香典は送る側の気持ちが重要です。喪主としては、相場からかけ離れた香典の額であっても気にしない人もいます。気になる場合は、後日の法要で菓子折りや供花などでお供えするのが良いでしょう。
職場の人が亡くなった場合や上司の家族などが亡くなった場合、告別式への参列は基本的に会社の判断に委ねられます。顔見知りの同僚が亡くなった場合でも、部内で選ばれた代表者のみが参列することもありますし、何人かで交代で焼香させてもらう場合もあります。個人で判断せずに、必ず上司の指示を仰ぎましょう。